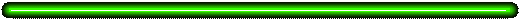
|
時計塔にある町
|
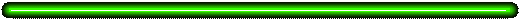
|
午前七時きっかりに目覚ましの音が鳴り響く。 大石は耳元で口やかましく自己主張をする目覚ましをひとつ小突いて黙らせると、ゆっくりと体を起こした。カーテンの間からもれる光で今日の天気を知る。今日も晴れだ。 一度起きてしまえば彼の行動は素早かった。いつもの作業着に着替え、洗面所に行き、食卓につき、作り置きの朝食を食べる。食べ終わる頃には、食卓の時計は七時半を指していた。急いで家を出る。 大石の家は古い造りのアパートである。外に出ると、同じアパートの住人が何人か外に出ていた。彼らも出勤の時間なのだ。 その中で、大石の隣の部屋に住んでいる顔馴染みの男が彼に声をかけてきた。 「おはよう、大石!」 「ああ、おはよう、平塚。いつも朝から元気いいな」 スーツの上着を脱いで小脇に抱えている平塚は、空いているほうの手で大石の背中を叩きながら、 「おう、それもお前のおかげだ。今日もよろしく頼むぜ、管理人さん!」 満面の笑みでそう返す隣人に、大石は曖昧な笑みを浮かべるだけで黙っていた。平塚は特に気に留めなかった様子で、「じゃあ、またな」と言ってアパートを出た。 大石はため息をついた。そして自分の格好を見下ろして、もうひとつ息をついてから歩き出した。 大石の職場は町の中心にある時計塔だ。時計塔といっても、中世の時計塔とは違い、基本的には普通の高層ビルである。ただやはり中世の時計塔のようにてっぺんに時計がしつらえられていて、しかもそれは四つ、ビルの四方にひとつずつ設けてあった。 だがこの町で時計塔の時計と呼ばれるのはこの四つではない。ビルの中にある「大時計」の方だ。大時計は、原子時計という周波数で時間を計る最も誤差のすくない時計であり、この町にある全ての時計とリンクしている。そして、ほかの時計が自分の示す時刻から狂わないように調整している。 つまるところ、この町にある時計は常にこのビルの時計の時刻と合わせてあるのだ。調整は時計塔から送信される電波によって行われる。この町の時計は、ほぼリアルタイムで自動的に大時計と同じ時刻に調整されるのである。よってその誤差は一秒にも満たない。 いつのころからは分からないが、この町の時計はすべて時計塔の電波を受信する電波時計になっており、町の人たちは常に同じ時刻を共有している。さらに、時計に内蔵されている電池も百年は持つ優れものばかりで、ソーラー電池も併用している。 そのためか、町の人たちの時間に対する信頼は厚く、考えは厳しい。時間は常に正しく刻まれていると思っている。遅刻など誰もしない。 ただ大時計の電波の影響か、町の外からの電波は届きにくかった。そのため、テレビなどは独立して放送するしかないのが難点ではあった。 大石はその時計を管理する時計管理局の人間だった。その中でも特に大時計から送られる信号を電波に変換し、町中へ飛ばす時計信号管理室に勤めている。大時計から送られる信号から、電波に乗せることのできるタイムコードを作成し、町へ飛ばすことのできる長波帯の電波に変換する。そうして作ったタイムコードが大時計の示す時間と同じになっているか確認する。その二つが主な仕事である。万が一にでも間違っていてはならない。この町では最も重要で、最も尊敬される仕事のひとつで、町の人が尊敬と親しみを込めて「管理人」と呼ぶ仕事である。 出社した大石を管理室の扉の前で待っている男がいた。 「準備はできてるか?」 大石が尋ねると、男は大石に小さな箱を手渡した。 「これで一応は予定の出力は出せるようになった」 大石は箱のふたを少し開けて中を確認した。間違いなく中には頼んでおいたものが入っている。 「ありがとう。じゃあ、また昼に」 「なあ」 男の声に、大石の足が止まる。 「本当に……やるのか?」 「……俺はやる」 大石の言葉は力強かった。 「分かった。なら最後まで付き合うよ」 「悪いな、ユウスケ」 堀田ユウスケは苦笑した。 「お前やケンジに振り回されるのには慣れてるよ。ほら行くぞ。もう、時間だ」 「……ああ。」 大石の返答は固かった。時間。今までこの町を裏で支えてきたそれが、いまやこの町を狂わせている。 二年前、大石と堀田の昔からの親友で、町の消防署に勤めていた三木本ケンジが殺された。 冬のよく晴れた日だった。その日の夜、町の某所で火災が発生した。担当だった三木本の署は通報を受け、五分で到着すると伝え現場に急行した。 彼らは通報から五分十二秒ほどで現地に到着した。だが、到着したころには火災にあった家はすでに火に包まれていた。通報が遅かったのか、冬の乾燥がいけないのか。しかもまだ中に人が残っているらしい。ともかく三木本ら消防隊員は迅速に消化の準備に取り掛かった。 ところが消火活動を始める消防隊員に対して、野次馬たちが暴動を起こしたのだ。彼らは口々に言ったという。 「早くしろよ!お前らが遅れた十二秒のせいで人が死ぬかもしれないんだぞ!」 「よりによってこんなときに遅れやがって!」 「たらたら準備してんじゃねえよ!」 野次馬たちはヒートアップし、消防隊員にペットボトルなどを投げつける者まで出てきた。三木本は上司に言われて、彼らを落ち着かせに行った。だが、特に激昂していた野次馬のひとりに石で頭を殴られ――絶命した。 当然裁判沙汰となったが、判決は懲役三年の実刑判決。殺人罪としては最も軽い罪だった。 裁判長いわく、「被害者所属の消防隊は事前に提示した時刻に遅れて現場に到着し、然るべき職務の遂行を怠っているのであり、被告が感情的になり錯乱していたことは当然のことと言える。また時間に遅れるのは人間としても消防隊員としてもあるまじき過失であり、以上の事情に鑑みて、被告の行為に酌量の余地があるのは言うまでもない」ということだった。原告側である三木本の家族は控訴し、現在は控訴審の判決を待つ状況である。 ちなみに、事件のあった火災では、結局死者は出なかった。 大石はこの判決を三木本の両親から聞き、憤慨した。ありえないことだと思った。言ってしまえば、遅刻したら殺されても仕方がない、と言っているのだ。この判決は。この町は。 それまでは何も感じなかった。正確な時間、規則正しい生活、時間を基盤とした能率的な仕事。この町で時間を守るのは当然だったし、遅刻した奴がいたら軽蔑したものだった。 だが時間が人の命より尊重されているという状況を知った。それから、大石の町を見る目は変わった。 サラリーマン達はいつも走り回っている。 時間が正確なため、時間を重視するようになったこの町では、分刻み、秒刻みのスケジュールなどザラだ。 遅刻したらまず相手方は話を聞いてくれない。早く行っても相手方の仕事の邪魔になり、いい印象は持たれない。それはいいのだが、この町のサラリーマンたちは、こう教えられている。 「完全に時間通りに行け。一秒でも早くも遅くも行くな。現場の近くまで行ったら、あとは歩調で時間を合わせろ」 相手方が完全に時間通りに来るということで、来てもらうほうも完全にギリギリまで仕事ができる。 結果として、ほかではありえないほどの過密スケジュールが出来あがる。 営業が帰る時間など、全てのグループが全く同時に帰ってくるので、ちょっとした行進のようになるほどである。 公園で遊んでいる子供がいる。 「じゃあちゃんと100数えろよ!」 そう言って一人を置いて散り散りに走り去る子供たち。かくれんぼをしているようだ。 鬼の子供は時計の針に合わせて100秒を数えると、走り出した。 瞬間、近くの茂みから一人の子供が現れて叫んだ。 「おい、まだ99秒しか経ってねえって!なあみんな!」 「そうそう、あと0,2秒くらいあるよ」 その近くのトイレの影から出てきた子供が同意する。 「じゃあお前、また数えなおしな!」 「遊ぶ時間、あと二十八分しかないんだからもう間違えんなよ!」 子供達はまたほうぼうに散っていった。 大泣きしている赤ん坊を母親があやしていた。 「どうしたの?おしっこ?」 赤ん坊は泣きやまない。 「ほら、ぶーぶですよー」 お気に入りのおもちゃを見せる。 赤ん坊は泣きやまない。 母親は焦っていた。早く泣き止んでほしい。 「もう、あと30秒で見たい番組が始まるのに……」 大石はそれまで、自分の仕事に誇りを持っていた。町の人たちの時間を守る。ひいては町の平穏を守る。自分たちが正しい時間を町に伝えることで、町の人たちが同じ時間にいることができる。この町で自分の仕事ほどやりがいのある仕事はないと思っていた。 だが、それは違ったのだ。結局のところ、大石が守ってきていたのは時間ではなく、時計の表示だった。そして絶対に確かな時計の表示があるせいで、町の人たちはいつの間にか時計の表示通りに動くのにことさら敏感になってしまっていた。問題は、その敏感さが自分以外にも向いているということだ。全てが時間通りに動くと思ってしまっている。 このままではいけない、と思った。それまで誇りを持って自分の仕事をこなしてきただけ、余計に大石はこの町の状況に罪悪感と責任感を感じた。 そして決心した。 この町の、時計塔を中心としたシステムの信用を根本から覆す。時計塔のシステムを狂わせ、時計が決して常に正しくないことを町の人に思い出してもらおう。このとき、誰にも気付かれないほうがいい。気がついたら時間が狂っていた、という方がショックが大きく、波及効果も高いだろう。 町の人が気付かないうちに、この町の正確な時間を奪う。この町から、「絶対に正しい時計」を盗むのである。 昼休み、大石と堀田以外の同僚が皆外に昼食を食べに行った。 常に時計を監視していないといけない時計管理局では、昼休みの時間に必要最小限の人間を残して休みに入る。昼番と言われるこの当番の人間は、ほかと少し時間をずらして休憩に入るのである。 昼休みの時間は一時間。大石と堀田は管理室の入り口に鍵をかけ、顔を見合わせると、同時に深く頷いた。 ふたりの「時間盗み」が始まる。 まずは堀田が管理室の防犯カメラに細工をする。これから一時間の間は、数週間前に撮っておいた映像が防犯カメラに流れるはずである。 「さて、最初の難関だな」 大石が局長の机の前で呟く。目的を達成するためには、大時計のある原器室に入らなければならない。原器室の鍵は局長の机の引き出しにあるのである。 用意しておいたピッキング用の工具を取り出す。この一ヶ月、ひたすら自室で練習してきた。できるはずだ……大石は自分に言い聞かせると、工具を鍵穴に差し込んだ。 一つ目の工具で、鍵の内部に隙間を作る。ここまでは簡単だ。次いでもうひとつの工具で鍵ケースを動かさなければならない。これが難しく、練習ではこれに八分もかかっていた。 急いで隙間に工具を差し込む。だが、上手く入り込まない。練習ではこれは一発で入るようになっていた。所要時間ニ秒ほどだ。大石は焦っている自分を自覚した。まだ時間はある、とゆっくり深呼吸をして落ち着かせる。二度目はすんなり奥まで入ってくれた。だがここまでにニ十三秒もかかってしまった。 指先の感覚と耳を頼りに、鍵ケースを動かそうとする。なかなか動かない。いい位置にはまれば、すんなりと鍵は開くのだが。十秒……二十秒……一分。時間ばかりがどんどん過ぎていく。遅れた時間を取り戻そうと、余計に手元が雑になっているのが自分でも分かった。だが、もう八分を二分は遅れてしまっている。 「急げ、モトヒロ! もうニ十分経ったぞ!」 堀田の言葉に驚愕する。もうそんなにも経っていたのか。手のひらには汗がじっとりと浮かび、もう開錠は無理なのではないかと思えてくる。 大石はもう一度深呼吸をしながら、三木本のことを考えた。馬鹿な奴だった。妙に真面目なところがあり、一度三人で海に行ったとき、バーベキュー用のコンロを忘れたと言ってわざわざひとりで取りに戻ったりもした。そして戻ってきたと思ったら、今度は炭に火をつけるために用意したガスバーナーを忘れたと言って戻ろうとしたので、慌てて大石と堀田で止めたのだ。火は新聞紙や潅木で四苦八苦してつけたのを憶えている。 三木本の無念を晴らす、という思いがないわけではない。むしろ、事件で死んだのが三木本でなかったら、自分はこんなことはしなかっただろうことを考えると、これは三木本の弔いのつもりでもあるのだろう。そこに思い至り、大石は苦笑した。 なんだ、要するに俺は、あいつがあんなことで死んだのが気に食わないだけじゃないか。 町の状況を看過できないという思いもある。だが三木本のようないい奴が二度と時間なんかを理由に殺されないために、というのが本音なのだろう。 だから、三木本。 大石はまた開錠にかかった。 ちょっと俺に力貸してくれ。 今度は落ち着いて手を動かすことができた。 「よし、開いた!」 大石が開錠に成功したのは、昼休みに入ってから二十八分後のことだった。あと三十ニ分。原器室で事を済ませた後、堀田がモニターやら何やらを誤魔化す時間を考えると、大石が使える時間は多くてあと十二分しかない。最初のうちに焦っていたせいで、練習より大幅に時間を食ってしまった。 引き出しを開け、原器室の鍵を掴み取る。鍵自体は何度か仕事で大時計の整備をするときに局長が使うのを見たことがあるので、すぐにどれか分かった。 全速力で原器室の扉の前に行き、大時計の居座るその部屋への扉を開けた。 大時計は相変わらず正確に時を刻んでいた。自分の腕時計も、管理室の壁掛け時計も、全てこの時計と同じ時刻を常に示している。つまりこの時計を狂わせれば、町中の時計は狂う。この町は信仰の対象である「絶対に狂わない時間」を失う。 大石は大時計に走り寄ると、その巨大な時計のカバーを取り外しにかかった。整備のときは簡単に取れていたと思っていたカバーが、今日はやけに粘ってくれる。 なんとかカバーを取り外すと、今朝方堀田に貰った箱を作業着のポケットから引っ張り出した。ふたを開けて中の物を取り出す。 それは小さなチップだった。このチップは、電流を流すと強力な電磁波を発する。周波数で時間を計る原子時計に電磁波は大敵だ。しかもこのチップは、堀田が調整して大時計にある一定の変化をもたらすように出来ている。 大石はその複雑な機械の中心にチップを取り付けた。 「大石、堀田、休憩入れ」 昼休みを終え、戻ってきた局長は開口一番そう言った。 大石と堀田は何事もなかったかのように「じゃあ失礼します」と席を立ち、時計塔を出てすぐの定食屋に入った。 まだ誰も彼ら二人がしかけた変化には気付いていない様子である。店内で、営業らしいサラリーマンが、時計を見ながらゆっくりとお茶を啜っていた。道路では主婦らしき女性が何人か固まって今日の三時からあるテレビ番組の話題に花を咲かせている。 いずれ、夕方にでもなれば町の人も気付くだろう。いつの間にか時間が過ぎていたことに。時計の進みがいつもよりほんの少し遅いことに。 大石と堀田が大時計に取り付けた仕掛けは、そのうち明るみに出て元に戻される。そのとき、時計の表示どおりに物事が進まかったと思い知らされた今日の出来事が、この町の何かを変えるかもしれない。 「じゃあ、日替わりをひとつ」 「俺も」 とりあえず、大石と堀田はゆっくりと遅めの昼食を食べることにした。以前は注文から料理が来るまでの時間経過にもイライラし、何かをしていないと落ち着かなかった。今はゆっくりと雑談でもしながら待っていることにしよう。 「お待たせしました、日替わり定食ですね」 テーブルに料理が運ばれ、ふたりは箸をとって食べ始めた。 「一仕事終わったあとの飯は最高だな」 「ああ、全くだ」 時間泥棒のふたりは、盗んだ時間をゆっくりと堪能していた。 |
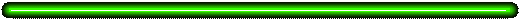
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
