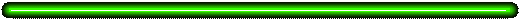
|
最期の一日
|
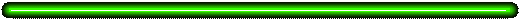
|
学校からの帰り道のことだった。 僕は、突然声をかけられた。 「あなたは明日死にます」 いきなりそんなことを言われても。正直、どんな対応をしていいのか分からない。 単純に無視してやろうかとも思ったけど、それを言ったのがかわいい女の子だったから、僕は一応耳を傾けてみた。 「なんで?」 「それを言うことは許されていないんです。ですが、あなたは確かに明日死にます」 「そう」 僕はそれだけを言った。別に明日死ぬなんて言われても、何も変わらない。明日のことは、明日にならなければ分からない。だから、別に明日死ぬかもしれないなんてことは、特別なことじゃない。誰もが、明日死ぬ可能性を持っているんだから。 「そこで、質問なのですが」 女の子の話はまだ終わってないらしかった。 「明日死んでしまうあなたは、今日何をなさるんですか?」 「別に普通だよ。死ぬかどうかなんて、明日にならないと分からないんだし」 「そうですね。普通は…そうです。ですが、あなたは明日死んでしまうことが分かっているんです。何をなさいますか?」 女の子は淡々と質問を続けた。 僕はとりあえず話を合わせて、明日本当に死んでしまうと思って答えを返した。 「そうだね…とりあえずは、貯金を全部使って、友達とかと思いっきり遊ぶかな」 「とりあえず?」 女の子は、意外なところを聞き返してきた。 「あ、うん。今思いつくのはそんな感じ。どうかな?」 「それであなたは満足して死ぬことができるんですか?」 今までより、少しだけ強い口調だった。どこか、悲痛な感じを受けるような。 「さあ…それはどうだろうね」 女の子は、ちょっとうつむいて。 「悠長にしていても、満足のいく死は迎えられないかもしれませんよ…」 僕はちょっと考えた。満足のいく死。突然明日死ぬことになっても、そんなもの、迎えることができるんだろうか…? ふと気づくと、女の子の姿は見えなくなっていた。周りを見渡しても、どこにもいない。 「え、あれ?」 どこにもいない。忽然と消えてしまっていた。そんな時間はなかったはずだ。 「明日は最期の一日です…よい一日を」 声だけが、さっきと変わらず聞こえた。 僕は背筋が凍りついた。女の子の得体の知れなさからもだけど、そんなことより、なにより、むしろ。 僕はもしかして、本当に明日死んでしまうのか? 家に帰ると、僕はとりあえず自分の部屋でベッドに寝転び、さっきのことについて考えてみた。 『あなたは明日死にます』 ……。 やはり、考えてしまえばそれはただのバカな話だった。明日誰が死ぬ、なんてこと、計画的な殺人でもない限りは分かるはずがない。 だけど、だからといって、僕に誰かに殺されるような覚えも価値もあるわけがない。 それに―― 『明日は最期の一日です…よい一日を』 あの言葉を言う前。彼女は確かに忽然と姿を消したのだ。 もしかしたら、彼女は僕の常識の通用しない存在なのかもしれない。不思議少女、というわけだ。 「なに考えてるんだか…」 我ながらバカらしい。何が不思議少女だ。そんなことで世の中の法則が覆せるわけもない。 だけど、もし。 あの子が本当に僕の死を予見しているのだとしたら。バカバカしいけど、そういう存在なのだとしたら。 僕は明日、死ぬことになっているのだ。 ……。 死ぬことなんて、どうでもいいとは思っていたけど。 いつ死んでも別にいいなんてこと思っていたけど。 なんだろう…やっぱり僕も、死ぬのは怖いってことなのだろうか。 やっぱり明日死ぬなんてこと、信じられない。だけど、もし死ぬのだとしたら、僕はもっとやらなきゃいけないこと――やりたいことがある。 死ぬのかどうかは分からない。でも死ぬなら、あの子が言ったように、満足して死にたいかもしれない。 だとしたら、僕が明日やらなければならないことは、ふたつ。 ひとつは、今まで世話になった人、親や友達に恩を返すこと。一日でできる限りのことをすれば、それなりに満足して死ねるかもしれない。 そしてもうひとつは、死なない方法を探ること。 やっぱり一日で満足して死ねるなんて思えない部分もあるし、明日死ぬなんてそう簡単に受け入れられない。なぜ死ぬのかは聞けなかったけど、とりあえず、これもできる限りのことはやってやろう。 …ただ問題は、これを二つともやってしまったら、多分どっちとも中途半端になってしまうことだ。 どちらかひとつ。これだけは、今日中に決めなければならない。 ……。 どっちが、いいんだろう? 正直ぜんぜん分からない。多分明日死ぬってことはないだろうとは思うから、できるだけ、普段の生活を壊したくはないんだけど。 …それなら、ふたつめか。 なぜ死ぬのか、それを突き止めて、回避する。普通に事故なら石橋を叩いて渡らないくらい気をつければ死なないで済むだろう。 決めた。僕は明日、なるべく普段どおりの生活をしながら、僕が死ぬ原因を探る。あるいは、死なないってことに確信が得られるかもしれない。 そうだな…明日は、ちょっとそういうこと、調べてみようか。 …ベッドに寝転んで考え事をしていたのは失敗だったかな…眠くなってきた。 さて、明日は最期の一日かもしれない。多分違うけど。朝は早めに起きようかな。 眠りから覚めて。 起きてみれば、実に平穏な朝だった。窓から指す光が、今日も晴れだということを教えてくれる。 どうということはない、普通どおりの一日だ。 だけど、今日は最期の一日になるかもしれないというのだから、やっぱり信じることはできそうになかった。 自分自身、あまり気にしすぎだとも思うが、昨日しっかり自分の中で決めたことだ。今日は、できる限りのことをしてやろう。 まず、部屋のパソコンを起動した。インターネットに接続して、メールをチェックしたら、僕はさっそく、最期の一日についての情報を集めることにした。 とはいっても、どうすればいいかは全く分からないので、とりあえずこんなことをしてみる。 …まぁ結果は分かっていたけど。 けど、そう簡単にあきらめる気分にもなれず、僕は一時、いろいろと試行錯誤して関係ありそうなサイトを探してみた。 結果は惨敗。カケラも手がかりはなかった。 …仕方ない。ちょっと学校の図書館ででも調べてみるか。 僕はとっとと切り上げると、準備をして学校に向かった。 うちの学校の図書館は、正直かなりの規模だった。確か、県下一という話を聞いたことがある。当然、蔵書の数も多くて、蔵書を検索するツールを使っても、全部に目を通すのには無理があった。 僕は一応、目に付いた本を何冊か持って、自習室の机に座っていた。 本の名前は、『死の予測』『人が最期に見るもの』『来訪』『絶望のとき』… こんなものを何冊も読んでいる時点で、周りからはかなり奇異に感じられるような題名ばっかりだ。 だけど、何冊か読み進めるうちに、僕はそうとう無駄なことをしている気がしてきた。 どこにも、参考になりそうな記述がないのだ。もう何冊目か…六冊目? にもなるというのに。 六冊目の本は、『西欧伝承録』とかいう、いかにもうそ臭い題名の本だ。 ぱらぱらと、ほとんど流すようにして目を通す。 はぁ… ため息ひとつ。やっぱり、この本にも関係のありそうなことは書いてない。 やっぱり、方法が悪いか。そんなあきらめも少し入りながら、僕は七冊目の本を手に取った。 『現代怪事件』。もう何か、笑いを狙っているのかと思えるほど偽物臭ただよう題名だ。 もう半分あきらめていた僕は、頬杖なんかつきながら、その本に目を通した。 やっぱり、ない。 「あーあ…」 僕はもう完全にやる気をなくして、イスの背もたれに寄りかかって大きく背伸びをした。 次は、どうするかな。新聞にでも目を通そ… 僕は一も二もなく飛びついた。背伸びしたひょうしに視界に入ったもの。 これもうそ臭いオカルト雑誌の表紙に、あの女の子が小さく小さく、載っていた。 その雑誌には、こんなことが書かれていた。 『死神の被害、すでに10名を突破』 『彼女に出会ったという投稿者が、100%の確立でその予告どおりに死亡した』 『死因は多様で、彼女に出会ったということ以外、被害者に共通点はない』 ……。 あとは、いかにもなあおり文句で、彼女の恐ろしさ――あるいは怪奇性を奉りたててあるだけだった。 …僕は、自分でも分かるくらい動揺した。全身から冷たい汗が一気にふきだし、体は抑え切れない戦慄にわなないた。 100%? もう10人以上も被害者が? ということは…ということは―― 僕は、ほんとうに、今日、死ぬ? 嘘だ。 そんなわけない。 そんなことが… そんなこと、本当なわけがない! 僕が死ぬ理由なんてどこにある? 体も健康だし、誰からも恨みを買うようなことはしていない! 交通事故なんてあうほど間抜けじゃない! 自殺なんてするような臆病者でもない! ありえない。他の奴ならともかく、なんで僕が死ぬことになるんだ!! 僕は、僕だけは…今日も明日も明後日も! 来月も、来年も、ずっと生きて――死ぬなんてことは、ずっとずっと先のことのはずなのに! 何かの冗談だろう? あんな女、疲れた僕が見た白昼夢くらいにしか思っていなかったのに! どうせ僕が死ぬなんてことはないと思っていたのに!! くそ、くそ、くそぉっ!! なんでだ! この図書館にいる周りの奴らは、きっと明日ものんきに生きているんだろうに! なんで僕だけが!! なんで僕だけが!! 僕は耐え切れなくなって、その雑誌を投げ捨てて図書館を走り出た。途中、係員が注意してきたけど、相手にしなかった。するはずがない。今の僕には、周りなんか関係ない。 ひとりになりたかった。 どこにいても、誰か人がいる。明日を生きて迎えられる奴らがいる。 そんなむかつく状況、耐えられるわけがない。 僕はあっという間に追い詰められた。雑誌に写真まで載っていたことで、半分夢のように感じていた女の子の存在が確証された。自分だけと思っていた状況に、陥った人が前にも何人もいて、しかも誰一人として、死を免れた人はいない。 もうこうなったら、僕が死んでしまうことは決まったも同然、むしろすでに予定事項だ。 頭の中から、世話になった人への恩返しなんて考えはとうに消えていた。もう僕にあるのは、生への執着と、生き残る人間への嫉妬のみ。 いや、もうひとつ。その二つの源ともいえるもの。 僕という存在が消えること。きっと、何も残らない。死んでしまうということは、結局、そういうことだ。他の人の中に思い出なんかは残るかもしれない。でもそれは、時が経てば薄れて、都合のいいように脚色されて――そこにいるのは、僕ではなくなってしまう。 その、哀しみ。 くそっ! ちくしょう…なんで僕だけが…! ……。 …僕だけ? いや…僕だけがいきなり死ぬなんて不公平なこと、誰が許しても、僕は許せない。 せめて、誰かひとりでも道連れにしてやる… 誰がいい? いっつも僕に偉そうに自分の考えを押し付けるあいつか? それとも、以前僕をこの上もなく傷つけてくれたあいつらか? いや… どうせ僕も死ぬんだ。どうせ殺すなら、そんな奴らじゃなく… あの子にしよう。僕が好きなあの子。まだあまり親しくなってないけど、でも何度か一緒に遊びに行ったこともあるあの子。きっと、このまま生きていればチャンスもめぐってきたのだろうけど、僕にはそんな猶予もない。 だから、僕は、あの子を殺して、そして、自分も死んで… 言ってしまえば無理心中か。それでもいいだろう。 決めた。 僕は歩き出した。きっと今日もあの子はいつもの場所にいるはずだ。 家の近くのコンビニ。あの子は、いつも昼までここでバイトしている。 さぁ、早く出て来てくれ。僕には時間がないんだ… 彼女が出てくると、僕は普段と変わりないよう気をつけて、話しかけた。 「やあ。今上がり?」 「え? あ、新村くん」 彼女は、僕の方を向くと、笑顔で返してくれた。 「どうしたの? わたしのこと、待ってたでしょ? 中から見えてたよ」 いたずらっぽく言って、くすくすと笑いをこぼす。 そんなしぐさひとつひとつに、僕はやっぱりこの子のことが好きなんだと確認させられる。 「ばれてたのか…いや、今日はちょっと、大事な話があって。時間取れる?」 「うん、いいよ」 彼女は二つ返事で了解してくれた。僕はそれじゃ、と言って、先に歩き出した。後ろから彼女がついてきてくれているのがわかって、少し安堵する。 さて、どこで殺してしまおうか… 自然と足は、人気のないほうに向いていた。 河川敷。 その中でも、特に人目につかない、川にかかっている橋の下。 僕は、そこを選んだ。 けど、それは失敗だったかもしれない。 橋の下には、先客がいた。 先客は、ぼーっと、川の方を見ている。男。スーツなんか着ているとこを見ると、きっとサラリーマンかなにかだろう。 僕は舌打ちして、その場を立ち去ろうとした。 ところが。 「おい…お前ら」 男が、急に声をかけてきた。 「…なんですか」 僕はいらだって男をにらみつけた。 なんなんだよこの男は。僕は今、人生の中で一番忙しいんだ。 「やけに幸せそうじゃねぇか?」 幸せそう? この僕が? もうすぐ死んでしまう、この僕と彼女が? 思わず、笑いがこぼれた。 「っにバカにしてやがんだ、コラァ!」 頭を貫く衝撃。僕はそんな感じのものを感じながら、やけに冷静に理解していた。ああ、殴られたんだな… 僕はそのまま倒れてしまった。頭がくらくらして、うまく立ち上がれない。 そうこうしている内に、男は彼女の胸倉をつかんでいた。そのまま、自分の方に引き寄せ、彼女の顔を凝視する。 やめろ。 男の顔に、下卑た笑みが浮かぶ。 やめろ。 その子は…僕が… 「…っく。ひっ…」 辺りには、彼女の泣き声だけが響いていた。 僕は、次第に消えていく川に広がった波紋を見つめながら、予定が狂ったことに呆然としていた。 だけど、まあこんなのもいいかもしれない。最期に、好きな女の子を守って、そしてそれから心中する。ふふふ、かっこいいじゃないか。 僕は波紋が完全に消えたのを確認すると、彼女の方に歩み寄った。 「大丈夫?」 一瞬の出来事だった。 泣いて座り込んでしまっていた彼女は、泣くのをやめると、はいずるようにして僕から遠ざかった。どこにそんな力があったのか、あっというまに距離を開けると、僕をおびえた目で見やった。 必死だった。 それはきっと、殺人者になってしまった僕と、あくまで被害者である自分との距離を開けるために。 そして、人を殺した「僕」という化け物の手の届かないところに逃げるため。 僕は、今度こそ完全に呆然とした。 なぜ。 そして呆然としているうちに、彼女はどこかへ逃げてしまっていた… 公園の公衆便所で、僕は顔を洗っていた。多少汚いのにも、もはや何の感情も浮かばない。 あの後。 僕は、大変なことに気づいた。 もし、これで僕が死ななかったら、どうなるのだろう…? 僕は殺人犯として世間から扱われるだろう。就職も、進学も、それどころか通学も、むしろ外を出歩くのもままならなくなるだろう。 それは、社会的に死んだも同然だった。 「ふふふっ。あはははははははは」 もう笑うしかなかった。結局は、もともと今日なんて、なんにもない普通の一日だったのだろう。 それを最期の一日にしたのは、僕。 僕は完全にそのことを信じてしまっていた。僕の中では、今日は僕が不思議な死を迎える最期の一日になってしまっていたのだ。 なんてことはない。結局は、僕の最期の一日なんてのは、なんでもない、ただの普通の一日だったってわけだ。 それを勝手な思い込みで、自分自身を追い詰めて…そして、取り返しのつかないことをしてしまった。 だけど、僕はまだ救われた。 今日で死んでしまうわけではない。 まだチャンスはいくらでもある。 きっと僕が殺人を犯したなんてことは、彼女の口から漏れるだろうけど。 けど、僕は未成年だから、死刑にはならない。ちょっと罪を償えば、簡単に社会に復帰できる。そこでは僕は最初死んでしまったままだろうけど、それでも、本当に死んでいるよりは楽しいことができるだろう。 未来は明るい。とりあえずは、自首でもしに行こう。 僕は、足取りも軽く、歩きだした。 と、外に出たところで、声が聞こえたような気がして僕は振り返った。 振り返った先には、顔も見たことがない女が立っていた。なにやら、ぶつぶつ言っている。 …なんだ? 「…で…たし…け」 「何で…私だけが…」 僕はすべてを理解した。 「最期の一日、よい一日を過ごせましたか?」 …その答えは、もう分かっているんじゃないのかい? 「そうですね…今までずっと、答えは同じでしたから」 それでも、あえて聞きたいと? 「いえ…一応聞いてみただけですから。おやすみなさい」 そういうと、少女は薄い笑みを浮かべて… 昨日と同じように、忽然と消えてしまった。 ▼あとがき▼ この話はある小説サイトをみて、「なに真面目な話ばっかり書いてやがるんだコイツはー」と思ったFOEが、気分の時間つぶしのために書いたお話でして、テーマは「満足のいく死」ですな。 ある友人がですね、「俺は今死んでも別に後悔しないと思う」とか言ってたんで、それはどうだろう? と思って書いてみました。勢いで。 本当に毎日その日に書いてたので、構成とかはめちゃくちゃです。主人公の行動の理由付けもしっかり考えてませんが、いちおう書いてしまったものは仕方ないのでアップした次第です。気分でも宣言してるし。 機会があれば続編も書けるんじゃないかなー、と思う今日この頃です。 ありえないとは思いますが、批評・感想などありましたらこちらまで。 |
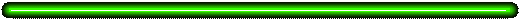
| SEO | [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送 | ||
